目次
この記事でできること
- printfをそのまま使うのではなく、ログ基盤として拡張できる
- どのモジュールのログか一目で分かるTAG付きログを実装できる
- 起動時にハード異常を検出するPOST(自己診断)を追加できる
- 「沈黙しないファームウェア」の土台を構築できる
はじめに
STM32 & 組み込みC言語開発が面白くて沼にハマりかけているgoldear@JiN_C125です。

前回(入門③)ではUART/USARTでprintfデバッグができるようになりました。しかし、printfをそのまま使い続けるだけでは「使い勝手が悪いな」とも感じました。
具体的には以下の通りです。
- ログが増えると読みにくい
- どこから出たログか分からない
- 重要なエラーが埋もれる
- 起動時のハード異常に気づきにくい
この問題を解決するため、printfを「ログ基盤」として拡張していきます。
本記事では、ログレベル管理・TAG運用・起動時POST(自己診断)を実装し、沈黙しないファームウェアを作っていきます。
開発環境
- 開発基板: STM32H723ZG
- 開発環境: STM32CubeIDE
- MCU設定: STM32CubeMX 設定済み(UART出力は入門③参照)
- microSD: SPI接続
- OLED:I2C接続
※ SDやOLEDの詳細実装は後続記事で解説予定です。本記事ではログ確認用途としてのみ使用します。
全体の流れ
今回の構成は次のとおりです。
- printf(UART出力)
- ログ基盤(utils/log.c)
- LOG_INFO() などのAPI経由で出力
- 起動時POSTで状態をまとめて表示
アプリ側からprintfを直接呼ばず、必ずログAPI経由で出力する設計にします。
Step1. ログ基盤ファイルを作成
utils配下に log.c / log.h を追加します。
<project>/
├─Core
├─Src
| └─utils
| └─log.c
├─Inc
└─utils
└─log.h
※ utils フォルダは自分で作成してください
まずはログレベル定義とAPIを作成します。
#pragma once
// --- include ---
#include <stdint.h>
// --- define ---
// コンパイル時ログレベル(ここを変えると不要ログはビルドから消えます)
#ifndef LOG_COMPILETIME_MIN_LEVEL
#define LOG_COMPILETIME_MIN_LEVEL LOG_LVL_INFO
#endif
// --- typedef ---
typedef enum
{
LOG_LVL_DEBUG = 0,
LOG_LVL_INFO,
LOG_LVL_WARN,
LOG_LVL_ERROR,
LOG_LVL_FATAL,
LOG_LVL_NONE
} log_level_t;
// --- function prototype ---
void log_printf(log_level_t lvl,
const char* tag,
const char* file,
int line,
const char* fmt, ...);
// --- macros ---
// file/line を自動付与して log_printf() に集約します
#define LOG_INFO(tag, fmt, ...) \
do { \
if ((LOG_LVL_INFO) >= LOG_COMPILETIME_MIN_LEVEL) { \
log_printf(LOG_LVL_INFO, tag, __FILE__, __LINE__, fmt, ##__VA_ARGS__); \
} \
} while (0)
※ 例として LOG_INFO のみ掲載していますが、
LOG_DEBUG / LOG_WARN / LOG_ERROR も同様の形式で定義しています。
- ログレベル(DEBUG/INFO/WARN…)をenumで定義し、重要度を扱えるようにしています
- LOG_COMPILETIME_MIN_LEVEL により、不要なログをコンパイル時に削減できます
- LOG_INFO() などのマクロから __FILE__/__LINE__ を自動付与して log_printf() に集約しています
このファイルでは以下の役割を持たせています。
- ログレベル(DEBUG / INFO / WARN など)の定義
- コンパイル時に不要ログを削除する仕組み
- printfを直接呼ばず、LOG_INFO() などのAPI経由で出力するためのマクロ
printfを直接使うと、ログの書き方が人それぞれになり、後から読んだときに非常に分かりにくくなります。
そこで出力方法をログAPIに統一し、常に同じフォーマットで表示されるようにしています。
Step2. コード実装(ログ本体)
次は printf をラップして、ログフォーマットを統一します。
このファイルの役割はシンプルで、次の3点だけです。
- ログレベルによるフィルタリング
- TAG付きの統一フォーマットで出力
- printf を最下層のI/Oとしてラップ
// --- include ---
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
#include "utils/log.h"
#include "stm32h7xx_hal.h"
// --- variable declaration ---
static volatile log_level_t s_runtime_level = LOG_LVL_DEBUG;
// --- function prototype ---
static const char* level_to_str(log_level_t lvl);
// --- functions ---
void log_set_runtime_level(log_level_t lvl)
{
s_runtime_level = lvl;
}
static const char* level_to_str(log_level_t lvl)
{
switch (lvl)
{
case LOG_LVL_DEBUG: return "DBG";
case LOG_LVL_INFO: return "INF";
case LOG_LVL_WARN: return "WRN";
case LOG_LVL_ERROR: return "ERR";
case LOG_LVL_FATAL: return "FTL";
default: return "UNK";
}
}
void log_printf(log_level_t lvl,
const char* tag,
const char* file,
int line,
const char* fmt, ...)
{
// コンパイル時ログレベルでフィルタ(不要ログはここで捨てます)
if (lvl < LOG_COMPILETIME_MIN_LEVEL)
{
return;
}
// 実行時ログレベルでフィルタ(動的に出力を絞れます)
if (lvl < (log_level_t)s_runtime_level)
{
return;
}
// 時刻(ms)
uint32_t tick = HAL_GetTick();
// ヘッダ:時刻 + レベル + TAG + 発生箇所(file:line)
printf("[%06lu][%s]", (unsigned long)tick, level_to_str(lvl));
printf("[%s]", (tag != NULL) ? tag : "--");
printf("[%s:%d] ", (file != NULL) ? file : "?", (file != NULL) ? line : 0);
// 本文(printf互換)
va_list ap;
va_start(ap, fmt);
vprintf(fmt, ap);
va_end(ap);
printf("\n");
}
- コンパイル時+実行時の2段階フィルタで、不要なログを出さないようにしています
- ログの先頭に 時刻(HAL_GetTick) を付けて、タイミングを追いやすくしています
- TAG と file:line を付けて、どこで何が起きたか追跡しやすくしています
- 本文は vprintf を使い、printfと同じ感覚でログを出せるようにしています
Step3. 動作確認
main.c からログAPIを呼び出して、実際に出力されることを確認します。
初期化後、無限ループの中など、好きな場所で構いませんが、今回は分かりやすく while(1) の外に1つ、中に2つ記述します。
#include "utils/log.h"
int main(void)
{
HAL_Init();
SystemClock_Config();
// ここに追加
LOG_INFO("BOOT", "system start");
while (1)
{
LOG_INFO("MAIN", "hello log");
LOG_WARN("TEST", "warning sample");
HAL_Delay(1000);
}
}
以下が出力例です。
[000001][INF][BOOT][main.c:20] system start [001001][INF][MAIN][main.c:25] hello log [002001][WRN][TEST][main.c:26] warning sample
※ これは出力例です。重要なのは、ログが常に同じフォーマットで出力されることです。tick値や file:line は変動します。
- ログレベル(INF / WRN)が表示されます
- TAG(MAIN / TEST)で出力元が分かります
- file:line により発生箇所を特定できます
- 時刻(ms)付きなのでタイミング解析にも使えます
printfと違い、常に同じフォーマットで出力されるため、後からログを追うのが非常に楽になります。
Step4. 内部解説(POST自己診断を入れる)
ログの真価は、起動時チェック(POST: Power On Self Test)で発揮されます。
組み込み開発では、外部モジュール(SDカードやOLEDなど)の接続不良・はんだ不良・差し忘れが頻繁に起きます。
そのため、起動直後に「今日の状態」を1行で報告させておくと、トラブルシュートが非常に楽になります。
ただし本記事の段階では、SD/OLEDのドライバ実装はまだ公開していません。
そこで今回は、POSTの“器”(結果を受け取ってまとめて表示する仕組み)だけを先に作ります。
- SDカード/SPIやOLED/I2Cの実装は後続記事で解説します
- 本記事では「POSTの考え方」と「まとめログの形式」を示します
app/boot.c └ POSTを実行して結果をまとめてログ出力 drv/sd_spi.c (後続記事) └ SD初期化 utils/sd_selftest.c(後続記事) └ FatFs read/write/verify drv/oled_i2c.c (後続記事) └ OLED probe/init
次のようなステータス構造体を用意し、各チェック結果を格納します。
typedef struct
{
uint8_t sd_ok;
uint8_t fat_ok;
uint8_t oled_ok;
} post_status_t;
最終的に起動時に、結果を1行でまとめて出力します。
LOG_INFO("BOOT", "POST: SD=%s FAT=%s OLED=%s",
st.sd_ok ? "OK" : "NG",
st.fat_ok ? "OK" : "NG",
st.oled_ok ? "OK" : "NG");
[000123][INF][BOOT][boot.c:xx] POST: SD=OK FAT=OK OLED=NG
※ これは出力例です。tick値や file:line は環境やコード位置によって変わります。
重要なのは、起動直後に「今の状態」が1行で分かることです。
沈黙するFWは信用できません。まずは起動直後に状態を報告させます。
Step5. ハマりポイント・注意点
ログ基盤を入れずにprintfだけで開発を進めると、次のようなトラブルが発生しがちです。
Q. ログが増えてきたら、何が起きているのか分からなくなりました
A. printfを直接呼んでいるとフォーマットが統一されず、ログが読みづらくなります。LOG_INFO() などのAPIに統一しましょう。
Q. このログがどこから出たのか特定できません
A. TAGや file:line が無いのが原因です。出力元情報を必ず付与しましょう。
Q. DEBUGログを大量に出したら動作が重くなりました
A. printfは意外と重い処理です。ログレベルで出力を絞る設計にすると改善できます。
Q. 起動時に動かないことがあるのに原因が分かりません
A. POST(自己診断)が無いと、外部モジュールの接続不良に気づけません。起動時チェックを入れておきましょう。
ログ基盤は「後から追加するもの」ではなく、「最初に作る土台」です。
まとめ
今回は printf を拡張し、ログ基盤を実装しました。
この記事でできるようになったことを整理すると、次の通りです。
- TAG付きで統一フォーマットのログを出力できるようになりました
- DEBUG / INFO / WARN などのログレベル管理ができるようになりました
- file:line や時刻付きで発生箇所を特定できるようになりました
- 起動時POST(自己診断)でシステム状態を一目で確認できるようになりました
これらを最初に整備しておくことで、
- デバッグ時間の短縮
- 原因特定の高速化
- 外部モジュールの接続ミスの早期発見
- 後から機能追加してもログが崩れない
といったメリットが得られます。
printfは単なる出力手段ですが、ログ基盤は「開発効率を左右する土台設計」です。
沈黙するファームウェアは信用できません。まずは喋らせるところから始めてみてください。
次回は、今回POSTの中で触れた OLED(I2C接続)を実際に動かして表示を行う方法 を公開予定です。ログ基盤と組み合わせることで、状態表示付きの実用的なデバッグ環境を構築していきます。
前回

次回: (準備中)
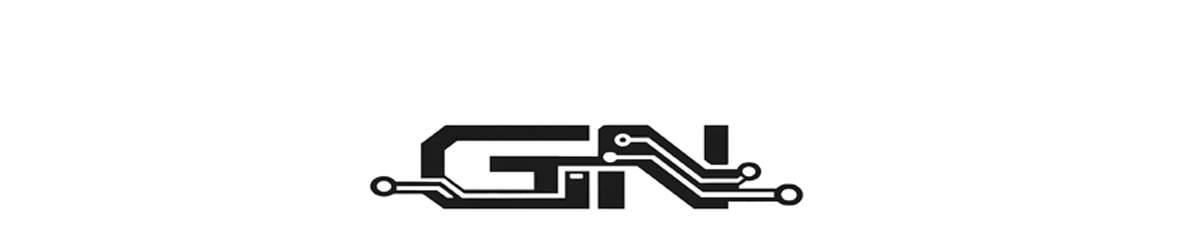
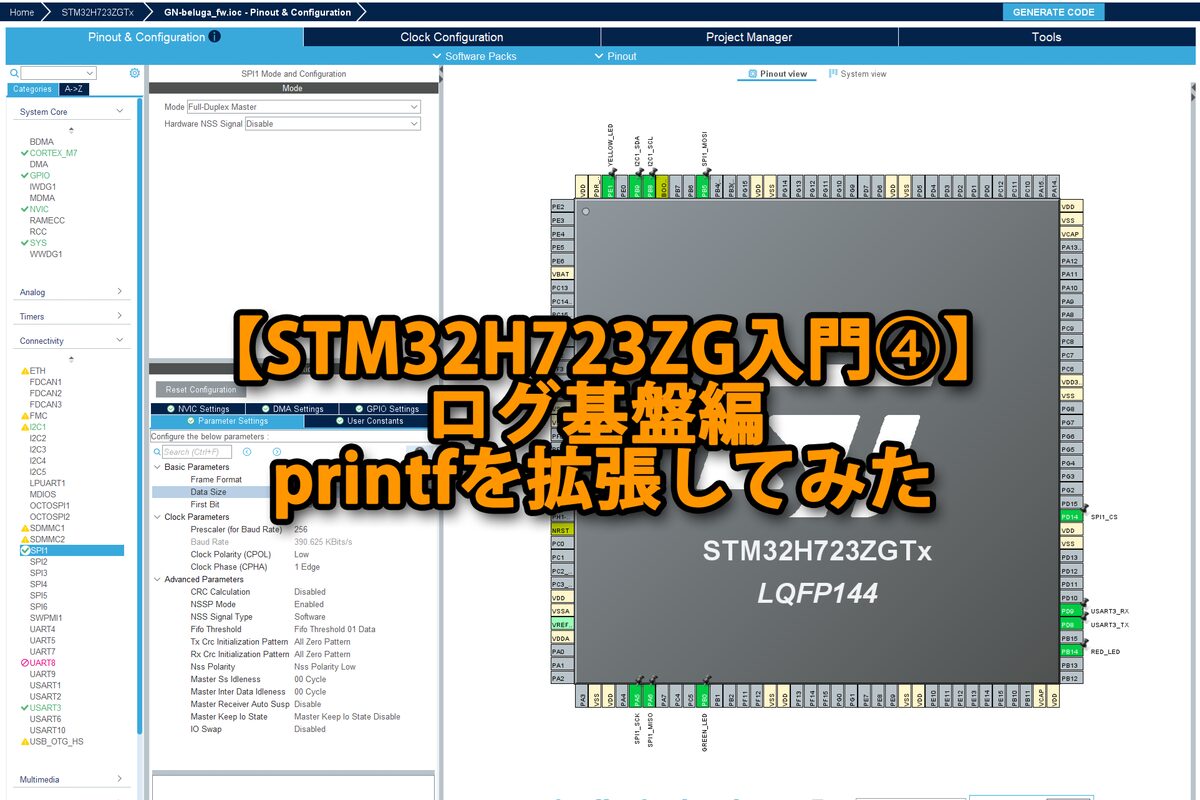
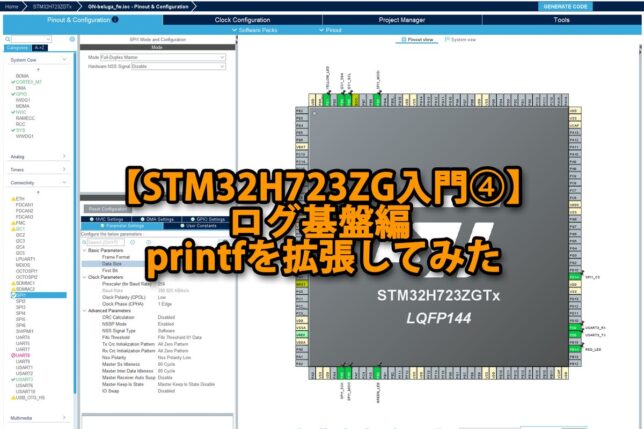


コメント